「世界人権宣言」は、人権尊重における「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、1948年12月10日、第3回国連総会の決議として宣言されました。
「世界人権宣言」は、20世紀に起こった二つの大戦への反省の下、世界が平和であるために、各国政府が達成すべき共通の基準と考えられています。法的拘束力をもつものではありませんが、さまざまな国の憲法や法律にも取り入れられています。
世界人権宣言
前文
世界人権宣言の前文は、すべての人が、平等で尊く、一人ひとりが、人権を持っていると認め、尊重することが、世界における公正、公平、そして平和の礎であるとのべます。これは、人類が戦争による破壊と悲惨を経験して学んだことです。世界における人権と自由の保障は人びとの願い。すべての国と人びとが「達成すべき共通の基準」としての人権。国連の加盟国は、人権と基本的自由を守り、さらに広めることを約束しています。人びとの間に人権の理解と尊重を根づかせるためには教育が大切です。世界人権宣言は、そのような思いを込めています。

第1条 人としての自由、尊厳、権利
人は、一人の例外もなく、自由で、かけがえなく尊いもの。すべての人が平等に人権を持っています。人間には、学び考え判断する力と、すべきことを勧め、すべきでないことを避けるようにうながす心が備わっています。仲のよい人や仲の悪い人、好きな人や嫌いな人、敵や味方がいても、だれをも人として大切にすべきです。
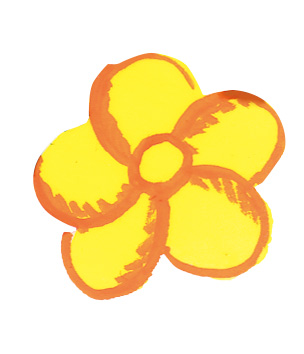
第2条 差別は絶対にだめ
人は、どんな理由によっても差別を受けることはありません。差別されないで自由に生きる。世界のどこに住んでいても、だれもが持つ人権です。差別はとくに社会的に弱い立場に置かれている人びとに向けられます。また差別は、しばしば複雑に絡みあって起こります。これは複合差別、差別の交差性などといわれます。差別される人にしかわからない苦しさ、つらさ、悔しさ。人として大切にして! 人権の訴えです。

第3条 一つしかない生命
むやみに奪われない生命。生命が守られなければ、生きていなければ、人はほかのすべての人権の保障を受けることができなくなります。その意味で生命に対する権利は、その他すべての人権の要といえるかもしれません。
大切な生命があからさまに奪われる場合があります。一つは、戦争や武力抗争です。もう一つは死刑です。これは生命に対する権利の侵害にはならないのでしょうか。
人は、ただ生きているというだけでは十分ではありません。自由に、安らかに生きる、それもだれもが持つ権利です。

第4条 奴隷にされない権利
人間は売り買いされる物ではありません。奴隷とは、人として大切にされず、自由を奪われ、利用され、こき使われる人間のこと。そのようなことは、絶対にあってはなりません。
いまでも形を変えて、人が奴隷のように取引されることがあります。「人身売買」とか「人身取引」とかいわれるものです。多くの場合、国境をまたいで行われます。人身売買の防止、加害者の処罰、被害者の保護、支援のためには国ぐにの協力が必要です。

第5条 拷問
どのような場合にも、人が人を痛めつけることは許されません。体を痛めつけ、精神的な苦痛を強いて、人としての尊厳を踏みにじる行為が拷問であり、非人道的なものです。そのような形の取り調べや刑罰もあってはなりません。

第6条 法の下で人として認められる
法律で定められた権利の行使、義務の履行は、法の下で人として認められて初めてできることです。人として認められる。すべての人が持つ人権です。
かつて人でありながら、法的には人として認められていなかった人びとがいました。いまだに女性が一人で契約を結べず、遺産を受け取れない国もあります。法の下で人として認められていないのです。
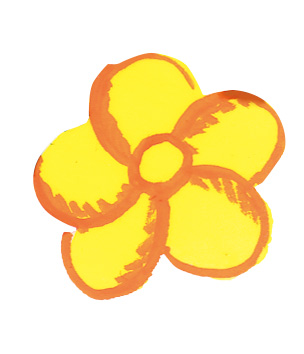
第7条 法の下の平等
法の下では、みんなが平等です。だれにも特権は認められませんし、だれも差別的な扱いをされることはありません。また、人には差別や差別を煽るような行為から保護される権利があります。差別から人をしっかり守ることができる法律が必要です。「差別をやめよう」とか、「人を傷つける言動をしないように」とか、言葉によるとりつくろいで差別をなくすことはできません。

第8条 被害者の救済
法律で守られるはずの正当な権利が守られなかったときには、裁判所に訴えて、法によって、侵害から守ってもらう、害をくわえる人を処罰する、償いを得るなどの救済を受けることができます。

第9条 身体の自由
人はだれでも、不当に、体の自由を奪われたり、どこかに閉じ込められたり、自分の居場所から追い出されたりすることはありません。これは法で守られる権利です。

第10条 公正な公開裁判
どんな人でも、公正な裁判を公開で受ける権利を持っています。裁判で使われる言葉がわからない人には、自分のわかる言葉に通訳してもらう権利があります。
政治権力から独立した裁判所による公開の裁判が守られていない国では、裁判所が政府に操られ、政府のために都合のよい判決を出したり、秘密の裁判でいつの間にか判決が下されたりすることがあります。このようにして、これまでしばしば人権が無視され、踏みにじられてきました。

第11条 無罪推定、罪と罰は法律で定められる
犯罪の疑いで訴えられた人は、裁判で有罪とされるまでは、無罪であるように扱われ、自分を弁護する権利が保障されます。逮捕されると、被疑者をまるで犯人のように扱い報道することが当たり前になってはいけません。また、法律で罪とされていないことをして罰せられることはありません。また定められた罰より重く罰せられることもありません。
これまで犯罪被疑者の取り調べで、罪を犯していないのに無理に自白させられて、有罪判決を受けることが起こりました。これを冤罪といいます。人権侵害です。冤罪を起こしてはなりません。
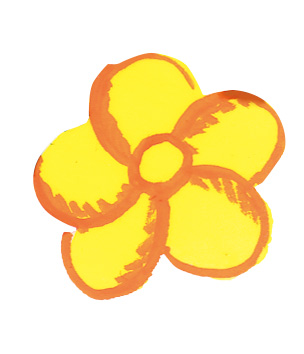
第12条 プライバシーの保護
自分や自分の家族のこと、私的な手紙や電話での会話などを探られたり、見られたり、盗み聞きされたりするなど、他人の干渉を受けることはありません。インターネットなどで手に入れる個人情報を本人の同意なく広めたり使ったりすることは、人権侵害です。
また、自分の名誉や信用を傷つけるような他人からの誹謗中傷も許されません。インターネット上にあふれる匿名の誹謗中傷もあります。このようなことをされた場合には、法律で守ってもらう権利があります。

第13条 移動の自由
自分の国のなかでは、どこに行くのも、どこに住むのも自由です。また、自分の国を出ることも、自分の国に帰ることも自由です。それは自分の権利であり、政府の許可がいるわけではありません。

第14条 迫害からの避難
自分の国で迫害される人は、国を逃れてほかの国に助けを求め、そこで保護してもらう権利を持っています。国によっては政府に反対する人を犯罪人として処罰することがありますが、そういう場合を除き、一般的な犯罪をおかして国外に逃れてこの権利を主張することはできません。

第15条 国籍
人はだれでも国籍を持つ権利があります。国籍は自分のルーツや自分らしさ(アイデンティティ)を確かめる大切な手がかりであり、国民としての権利や義務の裏付けとなるものです。そのような国籍を国が独断で奪うことは許されません。また、ほかの国の国籍を得て自分の国の国籍を離れることを自分で自由に決めることができます。

第16条 結婚、家庭
おとなになったら、男性も女性も自由に結婚し家庭をつくる権利を持っています。肌の色や国籍、宗教的な理由などには一切しばられません。結婚をするのは当事者二人、だれかからの押し付けで決められることはありません。しかし、いまでも当事者どうしが決めても自由に結婚できないことがあります。
結婚は公に認められた当事者の持続的なかかわりです。そのような人と人とのかかわりは、同性の間でもしだいに認められるようになってきました。
結婚でも、離婚でも、当事者の持つ権利は平等です。
家庭には、社会と国によって大切に守ってもらう権利があります。
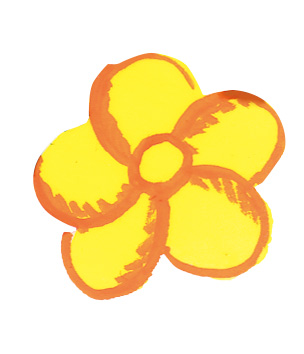
第17条 財産
だれにも、一人でもほかの人といっしょにでも財産を持つ権利があります。財産は、財産を持っている人以外だれも勝手に処分できません。夫が妻の財産を勝手に処分したり、親が子の貯金を無断で使ったりすること、家族のなかでもそのようなことは許されません。

第18条 思想、良心、宗教の自由
自分が心のなかで何を考え、何を思うか、またどのような信念を持ち、あるいはどのような宗教を信じるかは、まったく自由です。だれからの強制も制限も受けることはありません。自分の信念や宗教的な信仰を形や態度であらわすこと、そして宗教行事に参加することも自由です。この人権のことを「内心の自由」ともいいます。

第19条 意見•表現の自由
人はだれでも、だれからも干渉されずに自分の思いや考えをさまざまな手段で表現する権利を持っています。また、ほかの人と考えや思いをやりとりし、情報を探し、手に入れ、広く発信することも自由です。国境を越えて思いや考え、情報を伝えることも自由です。
この権利は大切な人権ですが、憎しみや人を著しく傷つけるような表現(ヘイトスピーチ)を社会で撒き散らすような行為は、「表現の自由」として守られるものとは考えられません。インターネット上では、さまざまな扇動や偽の情報などがあふれています。それらを見分ける力(インターネット・リテラシー)を備えることが大切です。
国が持つ情報は、市民生活に深くかかわることでも市民の手に届かないところで保管されていることが多く、情報開示を求め、知ることは、開かれた社会を守るためには大切な人権です。
「報道の自由」は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどメディアに認められるものです。メディアには、さまざまな圧力から自由で独立した情報発信が保障されるべきです。

第20条 集会•結社の自由
人は、自由に集まりを企画し、参加する権利を持っています。しかし、集会を開くことやこれに参加することを強制されることはありません。予定された集会が、圧力や脅し、いやがらせのために開くことができない。それを見過ごす国や自治体であってはなりません。
また人は、目的を持つ団体をつくることは自由です。すでにある団体に参加する権利も持っていますが、団体にくわわることを強制されることはありません。

第21条 政治にかかわる権利
市民が自分の生活にかかわる国、地方、地域のことを決めて自分たちの大切な生活を守るのは、政治に参加する権利、人権です。人びとの意見が反映される政治のために必要な権利です。
人間の長い歴史では、しばしば政治的な扇動や、実のない約束をばらまく人が権力を握りました。不幸な出来事です。そのような社会の流れに惑わされないように政治に参加することが大切です。
選挙は、人びとの考えを反映させるものとして、定期的に、投票の内容を他人に知られることなく、自由に票を投じることを前提として、公正に行われなければなりません。選挙する資格には、差別的な制限を設けることはできません。
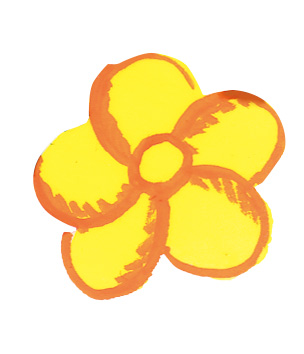
第22条 社会保障
人間としてふさわしい生活がむずかしくなったときに、みんなで助けあう。社会における人と人のつながり、目に見えない絆を見える形、制度にしたものが社会保障です。社会のだれもがそれに助けてもらう権利を持っています。「施し」を受けるわけではありません。
国は、人びとが人間らしく生きることができるように手だてを尽くす義務があります。社会保障は、国が優先順位で後回しにしてもよいものではありません。国がその義務を果たせない状態にあるときには、国際的な協力が必要になることもあります。
生活の必要最低限の支援のほかにも、人としての成長と人格形成に欠かせないものがあります。人は、それを経済的、社会的、そして文化的権利として求めることができ、国にはそれに応える責任があります。

第23条 労働の権利
働くことはだれもが持っている権利です。仕事は強制されることなく自由に選ぶことができます。働く人はその仕事に対して正当な条件を求めることができます。
だれもが、同等の仕事に対しては、差別されず同等の報酬を受ける権利を持っています。働く人は、自分と家族が人としての誇りを持って生活できるだけの報酬を受ける権利を持っています。
働く人はだれでも、労働組合をつくり、またこれに自由にくわわって自分たちの利益を守る権利を持っています。

第24条 休暇、余暇
働く人には、休みが必要です。休みや十分な睡眠をとらず長い時間働きつづけることは、健康を害する原因になり、ひどい場合は生命を危険にさらします。給料を受けとりながら休暇を取るのは働く人の正当な権利です。また、仕事以外に、人間らしい生活のために余暇を持つことも働く人の権利です。
労働は、人間にとって大切な、人間らしい営みですが、人が仕事に振り回されて、人間らしい生き方を見失ってしまってはなりません。

第25条 生活水準の保障
だれもが、人としての誇りを持って生活できるように、衣食住と健康への配慮とふさわしい生活水準を保つための保障を受けることができます。これは人権です。
だれでも、失業、病気、体や心の障害、パートナーの死亡、高齢にともなうさまざまな問題が起こったときには、適切な施設と制度によって必要な治療や支援を受ける権利を持っています。
母と子には、手厚い保護と援助を受ける権利があります。子どもはどのような境遇に生まれるにせよ、同じ社会的保護を受ける権利があります。

第26条 教育についての権利
教育はすべての人にとって大切です。教育によって、人はそれぞれ自分にふさわしく成長し、自分の、そして他者の人間としての尊厳と人権を大切にすることを学びます。
教育は、国、民族、宗教などの多様性を尊び、平和のための働きをうながすことをめざします。情報や交通の手段の発達で、世界中の人びとが互いに接し、知りあう機会が増えています。どんな国に住み、どんな生活をしていても、互いに人として大切にしあうことができる。このようなことを目標とする教育が必要です。すべての人はそのような教育を受ける権利を持っています。
初等教育はみんなが受けるよう求められ、無償です。また、すべての人に、それぞれの能力、意欲、適性に応じて、技術教育、職業教育、高等教育の機会が与えられなければなりません。
親は、子どもがどのような教育を受けるかについては、子どもの最善の利益を考えてだれよりも先に決める権利を持っています。
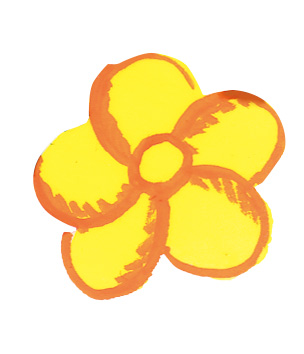
第27条 文化的な生活
文化、芸術は心の糧です。人はだれでも、豊かな文化に接し、芸術を鑑賞し、また文化的な活動に参加することで、人間としての生活を豊かにできます。また科学技術の進歩の恩恵も受けられます。人はこれらを人権として求めることができます。国や地方公共団体には、市民がこれらの恩恵にあずかることができるように、文化を保護し、文化活動や芸術活動を支援する責任があります。
また、自分が創作した作品、発明などについては、他人が模倣したり、盗んだりしないように、またそこから生まれる利益を守られるように求める権利を持っています。

第28条 社会の秩序、国際秩序
すべての人が持つ人権と自由が保障されるためには、国内や国際社会でそのための条件が整っていることが必要です。公正と公平にもとづく政治と行政の制度や仕組み、経済財政の運営、独立した司法などです。人はだれでもそのような社会秩序を求める権利を持っています。

第29条 社会に対する責務
人は、社会で人と交わりながら生きることによって成長し、それぞれにふさわしい生き方ができるようになります。同じ社会で生活する人びとの間の経済的、社会的格差が著しくひろがったり、生活する人びとの多様性が受け入れられなかったりすれば、社会が一つにまとまることはむずかしくなります。このような社会を壊してしまう原因を取り除くことは国の責任です。そして、人が大切にされ、人と人の絆がはぐくまれるような社会を守ることは、市民として一人ひとりの義務でもあります。
人が自分の権利と自由を行使しようとするときには、ほかの人も自分と同じように人権と自由を持っていることを認め、尊重しなければなりません。人びとが集まってつくる社会では、モラル、公の秩序、みんなの福祉のために、行動が規制されることがあるかもしれませんが、それは法律ではっきり決められて、必要最小限にとどめられなくてはなりません。
またどのような場合にも、人権と自由を主張しながら、国と国の平等、平和、民主的な社会体制などを否定したり、破壊したりするために行動してはなりません。

第30条 権利および自由を破壊する活動
世界人権宣言でのべられた権利と自由を否定するような活動をしたり、そのために行動したりする権利があると考えることはできません。
〈出典:「人権ってなんだろう?」一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター編著(解放出版社)/イラスト:いとう瞳〉