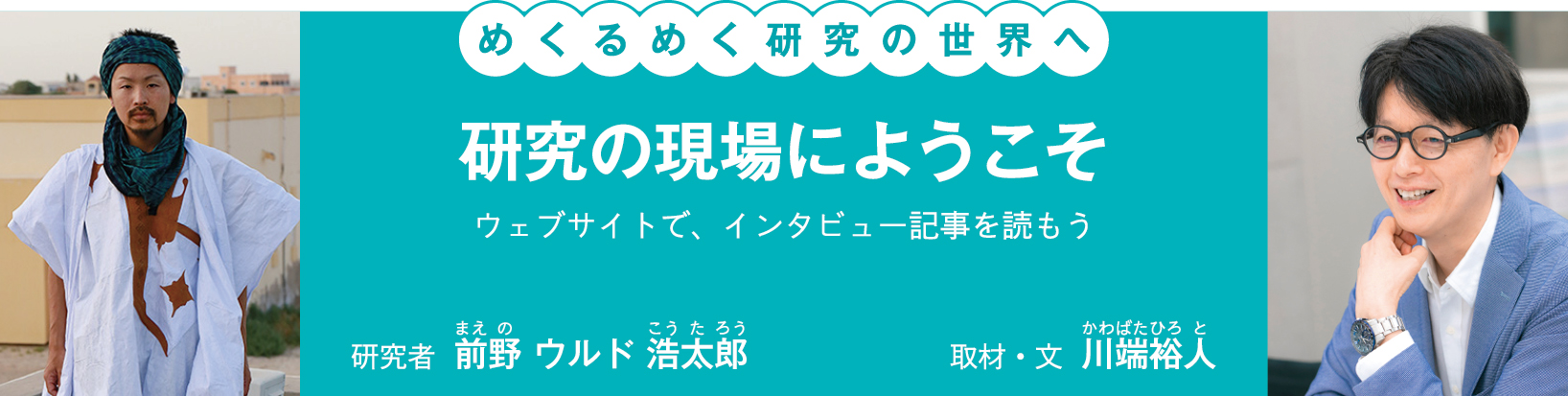第1回 | バッタ博士とモーリタニアの砂漠でバッタにまみれる
今回、訪ねたのは、西アフリカの砂漠の国、モーリタニア。
しばしば大発生しては、緑という緑を食い荒らす害虫、サバクトビバッタの研究者、前野ウルド浩太郎さんを訪問した。前野さんは、2011年からモーリタニア国立サバクトビバッタ研究所を拠点に調査研究をしている「日本人唯一」の(そして、「先進国唯一」でもある)野生のサバクトビバッタの研究者だ(2014年現在)。
前野さんと同行し、1泊2日でサハラ砂漠にキャンプに出かけ、最初に出会った光景を、まずご覧いただきたい。

サバクトビバッタの幼虫が写っている。バッタの幼虫だから、翅が飛べるほどに発達していない他は、成虫とそれほど姿形は変わらない。さて、バッタはどこにいるでしょうか。

現地から写真を送った時、編集者は「菜の花畑かと思った。」と述べ、友人は「どこにいるか一生懸命さがして、ぜんぶ! と分かった瞬間、ぞわっとした。」と言った。

なにはともあれ、これがサバクトビバッタとぼくのファーストコンタクトである。

帰国し、撮影した写真を眺めている今も、すごい生き物を見た! という純粋な驚愕と、しばしば人々を飢餓に陥れるほどの凶暴さを発揮するという、これまで文献で知っていた知識が「本当なんだ。」という妙な納得がないまぜになった、不思議な感覚にとらわれている。
この不思議の世界、サハラ砂漠でひたすら研究に明け暮れる前野ウルド浩太郎さんのこと、そして、彼の案内で体験できたことを、興奮が薄まらないうちに書き留めておきたい。
西アフリカ諸国へのハブ(注:中心。ここでは、その地域の拠点となる空港のこと。)になっているモロッコのカサブランカ空港から、モーリタニアの首都ヌアクショットへの便は深夜12時近くに到着する。
砂漠の国へやってきたと思いきや、機外に出た瞬間、空気が湿っていることに気づいた。それどころか、飛行機から降りてターミナルまで歩く間に、ぽつりと1滴頬に雨粒を感じた。
英語が通じにくいフランス語圏で、なおかつ厳格なイスラム国家。入国はそれなりに厳重で、目的は何かとか、アルコールは持ち込んでいないかとか、などさんざん質問された上で、やっと無事に入国スタンプを押してもらえた。

前野ウルド浩太郎さんが、駐車場で待っていてくれた。いわゆるポスドク(注:ポストドクターの略。主に博士号取得後に、任期を決めて、研究職に就いている人。)であり、抱腹絶倒のブログ「砂漠のリアルムシキング」や、昆虫研究者の本気と狂気(?)を垣間見せてくれる著作「孤独なバッタが群れるとき」(東海大学出版会)などで知られ、日本ではディープなファンがいる。今、最も認知度が高い、若手昆虫研究者と言って差し支えない。
「きょうは1日雨だったんですよ。自分が来てから3年目ですが、この時期に雨が降るのははじめてですね。こっちの人に聞いても、滅多にないそうです。」という。
ぼくが訪ねたのは11月で、1年の中でも乾燥が強くなりはじめる時期だそうだ。少量の雨が降る7月、8月とは違い、本来降雨はない。事前に前野さんからのメールで「日中は40℃、夜でも20℃くらいの気温です。」と言われていたけれど、それよりもずっと涼しい。おまけに湿っている。
そんなイレギュラーな天気の中で、砂漠らしからぬ砂漠の国への到着となった。
翌朝、曇天。
研究所のゲストハウスから、サハラ砂漠へ。
ランドクルーザー2台の編成で、1台は前野さんが雇っているドライバーのティジャニが運転して、後部座席に前野さんとぼくが乗った。もう1台は、テント、食料などをはじめとする物資を積んだ助手さんの車だ。

到着時は深夜だったために素通りしてしまった研究所の建物を、まずはしっかり確認した。正式名称は、Centre National de Lutte Antiacridienne。原義に忠実に訳せば、「国立・対バッタ類防御センター」みたいな名だ。物々しいゲートを開けてもらい、いざ出発。
研究所は町外れにあって、中心部とは逆側に向かう。当初は車通りがさかんで、ロバに荷物を引かせる「シャレット」の往来も多かったが、すぐに砂漠を貫く1本道になった。砂漠とはいえ、このあたりは、砂丘が連なる砂地ばかりのものとは違い、かなり草も生えている。たまたま多雨な年だというのも関係しているだろう。それでも森が出来るわけでも、草原になるわけでもない、まぎれもない砂漠だ。
町を出て1時間と少し、おそらく百数十キロほど離れたところで、ランドクルーザーは舗装された道路を離れた。ここから先は、高い車高と大きなタイヤ、四輪駆動がものをいう。砂漠には、前に通った車が作ったわだち(注:車輪の跡のこと。)はあっても、決まった道があるわけではないので、たえずGPSで現在位置を確かめつつ進むことになる。先発隊のいる座標は分かっていて、方向も間違いなく分かる。ただ、地面の状態によって、いつもまっすぐに進めるわけではない。

「結局、最後は目視でキャンプ地を探すんですよ。3キロくらいに近づけば見えてきますね。砂漠に白いテントは目立ちますから。」
我々が探しているのは、モーリタニアの遊牧民が使うものに似た大きな白いテント群だ。
それらを発見できずに移動するうちに、遠くに車がとまっているのが見えた。
先発隊のうちの誰かの車であるようで、そちらに近寄っていくと、ドライバーのティジャニが「Ici! Ici!(ここ、ここ!)」と指さした。
前野さんが、ニヤリと笑いぼくを見た。
「川端さん、運が良すぎですよ。さっそく、お見せしたかったものがいました。自分も、ここにきて、ちゃんと会えたフィールドトリップは、3年いる中でもこれで5回目ッス。」
車の中から目を凝らすと、赤茶けた砂地に背の低い草がところどころ密に生えていた。
そして、緑に紛れて、あるいは砂の裸地の上に、黄、緑、黒といった色がまざった小さなものが、もぞもぞと動いているのだ。
風に揺れる花、というのは、一瞬なら、そう錯覚することもありえる。
ただ、なすがままに揺れる動きとは違う。
地面をはう動物の群れだ。
スズメバチがアリのように地面の上でうごめいている、というのがぼくが抱いた最初の印象だった。
「これがサバクトビバッタの幼虫の群生相のマーチングですよ。幼虫の群れのことをバンドと言って、みんな同じ方向に向かって一斉に行進していく行動をマーチングといいます。本当に、よかった。とにかく、自分、これを見せたかったんですよ!」
前野さんは興奮して言った。
ぼくは夢中になって写真を撮ったわけだが、このファーストコンタクトはかなり強烈で、意識がぼーっとなってしまったほどだ。
それでも、一応、自分なりに観察をして気づいたことがいくつか。
背の低い地面を覆う植物の他に、所々、ツンツンしたイネ科植物のかたまりがある。そこには、たいていサバクトビバッタの幼虫がくっついて、なかほどまで登っていた。周囲の砂地には、黒いものがたくさん散っており、それはウンチであろう。また、近くにひとつだけ、「歯磨木」(あるいは、歯磨きの木。名の由来は後述)と呼ばれる灌木があり、そこにもかなりの数が潜んでいた。
「夜になると結構、こういうところに集まってくるんですけど、昼間からってのは、自分もはじめてッスね。本当にフィールドで、こいつらに会うたびに、新しい発見があるッス。」と前野さん。
前日は雨が降り、気温が上がらなかった。雨の中でもサバクトビバッタを見ていた先発隊に後で教えてもらったのだが、その間、幼虫たちは、こういった背の高い草や木に宿り、動かなかったそうだ。そして、この日も曇天で、せいぜい気温35℃前後。また、風も強かった。なにか特別な状況の日にたまたま来てしまったために、ぼくは前野さんとともに、特別な現象を見てしまったらしい。
前野さんが、車に戻り、捕虫網を持って来た。
「捕まえます。だいたい、300匹くらいは、必要ッス。」
サハラ砂漠で、捕虫網を振る「バッタ博士」こと、前野ウルド浩太郎さん。
サングラスをしていても、喜びが伝わってくるほどの躍動感で、バッタを白い網の中に追い込んでいった。
本当に、楽しげである。
前野さんが必要な数を取り終えた後、ぼくも網を借りて少しだけ捕まえさせてもらった。
子ども時代に戻ったように、楽しいひとときだった。
とはいえ、このバッタが、実は「悪魔」と呼ばれるほどの凶暴さを発揮する、まさに直前の状態であることを思い出し、ふと現実に立ち返ったのだった。