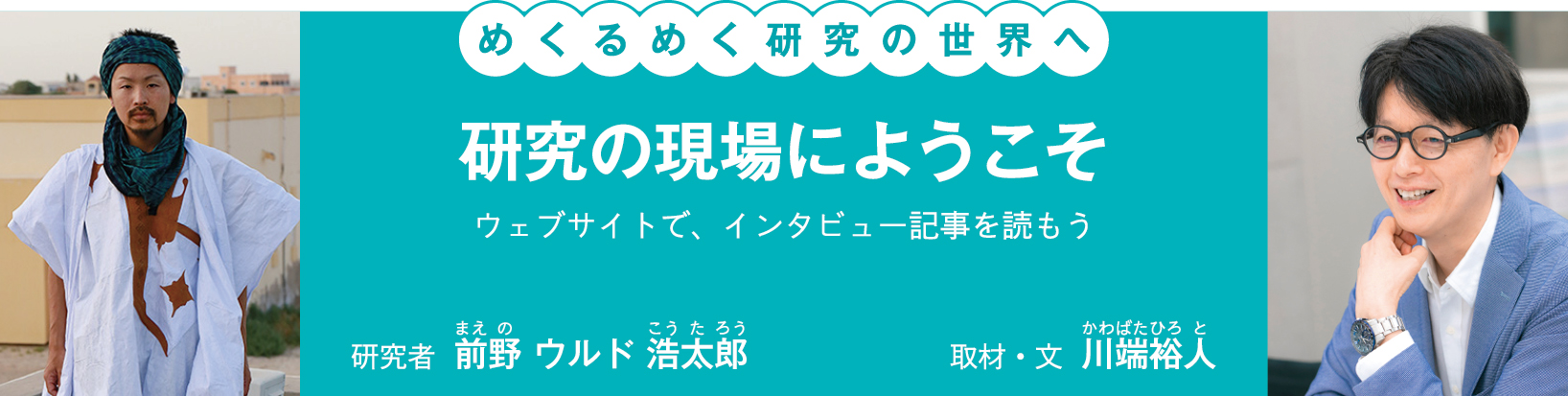第4回 | バッタ博士、モーリタニアへ旅立つ
日本の研究室でサバクトビバッタと運命的な出会いを果たした前野ウルド浩太郎さんは、野生のサバクトビバッタがいるモーリタニアのサバクトビバッタ研究所を拠点に選んだ。その背景には、それまで前野さんが「実験室」でのみサバクトビバッタを見てきたことに、少々、違和感を覚え始めたことにある。
「実は博士課程に入った頃から、このまま研究していってもはたしていいものかどうか、恥ずかしさとか後ろめたさを感じはじめていまして。よくよく考えたら、サバクトビバッタは現地でものすごい大発生をして、深刻な被害を及ぼしているわけじゃないですか。とするなら、野生のサバクトビバッタが何をしているのかを知ることが、結局自分の最終目的じゃないかと。相変異のメカニズムを知るとか、これまでのテーマをやっていく上でも本当の自然を知らなければ、間違ったところにたどり着いてしまうんじゃないか、そういう不安やフラストレーションがありました。それで、現地に行って研究して、なおかつ、アフリカのバッタ問題の解決に貢献できたらいいな、できるんじゃないかなって、最初は軽い気持ちです。」
軽い気持ちと本人は言うが、環境が整えられた日本の研究室から、えいやっと日本人がほとんど住んでいない砂漠の国へと旅立つのは、それなりの決意がいる。ポスドク(博士研究員)を支援する日本学術振興会の海外特別研究員という制度で、生活費と研究費はまかなえるものの、それも2年の期限付き。キャリアとして考えれば、賭け、ということになるだろう。
幸運だったのは、モーリタニア側の受け入れが、かなりしっかりしていたことだ。研究所内にあるゲストハウスを居室兼研究室として使えたし、なにより、研究所長のババ博士が日本からやってきた研究者を非常に歓迎してくれた。ババ所長には、ぼくも滞在中、3回ほどお会いしたが、バッタ防除についての責任を担って多忙であるにもかかわらず、常に笑顔で人を包み込む人格者だ。研究所で雇用する現地の職員の人望も厚い所長みずからが、前野さんの研究を大歓迎し、フルサポートしてくれた。


「ババ所長はいつもてんてこ舞いで、くたびれていてもバッタと闘うための準備を一生懸命やっているんです。それなのに、私のこともいろいろ励ましてくれるんですよ。日本のバッタ研究者がアフリカの現地に来て、腰を据えて研究をするのは初めてだそうです。それどころか、『見てみろ、浩太郎、今、先進国から誰も研究者が来てないぞ、おまえだけだぞ。』って。アフリカの人たちは浩太郎の研究面での活躍に期待しているんだとまで言ってもらえたんです。」
実際に、「先進国」のサバクトビバッタの研究者で、アフリカの現地を拠点にしているのは、前野さんだけなのだそうだ。ただでさえ研究設備が整わず不便な土地だ。それに加えて、旧宗主国(注:他国の内政や外交などを支配・管理する国のこと。現存するものはない。)であるフランスをはじめヨーロッパ系の研究者はテロの対象になりやすい(ぼくの訪問時、フランス大使館はフランス人が首都のヌアクショットから出ないように勧告していた。)などの、様々な要因もある。一方、アフリカ現地の研究者は、外国の大学で学位を取って研究のノウハウを身につけても、母国ではすぐに人の上に立って指揮をする立場になってしまう。前野さんは、ぽっかり空いた昆虫学のエアポケットに吸い込まれ、唯一無二の研究者として、砂漠の国に降り立ったのだった。
では、実際に現地でみるライブなサバクトビバッタはどうだったろう。
「衝撃的でした。今まで見ていたサバクトビバッタとは一体何だったのかっていうくらい。考えてみたら、実験室の31℃で一定に管理されている環境じゃないんです。温度にしても、昼間40℃以上にあがって夜は20℃に下がりますし、珍しく雨が降って日中でも35℃とかいう日もあります。その暑さ、風、いろいろな環境を感じて、適応した行動をするわけですよね。そういう素顔のバッタを見られたので、それだけでもう大収穫というか、驚きでした。」
前野さんが、サハラ砂漠での最初のフィールドで、いきなり衝撃に見舞われた様子は、著書「孤独なバッタが群れるとき」にも描かれている。実験室で飼育しているものではみられない行動を、あちこちで発見し、うわっうわっうわっとなりつつも、研究者魂を発揮し、調査初日の夜から、後に論文として結実する調査を開始する。
例えば──、
孤独相の野生のサバクトビバッタが、昼間はあちこちに散らばっているのに、夜、木に宿るのを見いだした。これまでにも、砂漠にはえている何種類かの草木をシェルター(注:避難所、安心して休める場所、といった意味。)にするという報告はあったし、前野さんの目には、とげのある灌木に多くの個体がついているように見えた。そこで、前野さんは、彼らがどのようなシェルターを好むのかを調べようと思い立った。
フィールドで疑問を感じたら、その場で、即、観察や実験開始! というのは、ファーブルの流儀である。ある昆虫やその行動に出会うのは1回限りかもしれない。それを逃さずに、きちんと観察するのは、フィールドワーカーの基本! なのだから。
「まるでファーブルみたい。」と自分に興奮しつつ、夜22時から午前2時までかかって、ランダムに選んだ区画の中の木々や草に宿るバッタを調べて回った。結果、バッタがとげのある灌木を好み、それも、灌木の大きさによって、集合する度合いが違うことがはっきり示された。大きな宿り木の方が好まれるのである。さらに後日別の場所でも同じ傾向があることも確認し、論文執筆に踏み切った。1日目にその場で疑問に思ったことを(前野さんに言わせれば「疑問の現地調達」)、その場で研究計画を立て、きちんと分析し、論文にする。フィールドの生物学者としてデビューした当日にここまでの成果を出すのだから、ファーブルの後継者を目指す者として、相当気合いが入っていたといえる。
さらに調査は続く。
「自分の本には、調査の1日目のことしか書かなかったんですが、あの時の調査旅行には続きがありました。次の日は孤独相のエリアからうって変わって、群生相の幼虫のマーチング・バンド、非常に大量のバッタに遭遇したんです。植物の上で休んでいる彼らに向かって接近すると、バッタがその植物の中に逃げ込むパターンと、その植物を見切って外に脱出して、跳ねて逃げていくパターンがあることに気づきました。何回か突撃を繰り返しているうちに、植物が大きいと安心してとどまるけれど、シェルターがしょぼいとすぐに見限って逃げる傾向がみえてきました。その日帰る予定だったんですけども、ここに残ってデータとりたいから、ちょっと待ってくれと研究所のスタッフに言って、そこで4日とどまって、毎日データをとって、これも論文になりました。」
論文のタイトルは「サバクトビバッタ群生相幼虫の、植物のサイズに依存的な逃避行動」といったもので、昆虫の行動学の専門誌に発表された。
最初の調査旅行で、いきなり論文を2報! なんと欲張りで、また、充実したフィールドワークであることか! 別に「論文のための論文」ではなく、現場で感じた疑問を、そのまま検証すべき仮説として組み直し、仮説が正しいか正しくないか確かめる方法を考えて実践する。まさに、原初的なフィールドワークの仕事なのだ。
ふと不思議に思ったのは、前野さんが、それ以前には、アカデミックな意味でのフィールドでの訓練をそれほど受けていないことだ。それなのに、ごく自然に、フィールドワークをして、きちんと論文に出来てしまうあたり、どうなのだろうか。直接、質問してみた。
「ぶっつけ本番がサハラ砂漠ですから、自分でも、最初びびっていたんですけども、やっぱり現地でバッタを見ると、すごいいろんな疑問がどんどんわいてくるんです。疑問にこたえるために、どんな実験をして、どんなデータをとればいいかという、お決まりパターンみたいなのがあります。いわゆる研究のお約束事みたいなものですね。自分はまだまだ未熟ですけども、優秀な先生たちに教えてもらったおかげでなんとかなっているんだと思います。特に砂漠に来ると、ネットもつながらないし、文献とか何もないので自分で全部その場でやらなければなりません。」


ゲストハウスの自室で、この取材中に捕まえた個体の体色が分かるようにスキャナーで記録をとる前野さん。ちなみにバッタはまだ生きていて、氷で体温を下げて動けなくしている。
実験室だと、厳密に条件を整えた、「きれいな」実験ができる。その場で思いついたらすぐ行わねばならない昆虫のフィールドワークとは一線を画すると思いきや、実は「研究のお約束ごと」というのはかなり普遍的でもある。何かを確かめたいなら、その現象を見るのと同時に対照となるものを見なければ比較しようがないとか、はっきりした結論を言うためには最低限どれくらいのサンプルサイズが必要とか、そのようなことは、考えてみれば共通なのである。
「今まで、生き物のフィールドワーカーの人たちの本なんかを読んで、すごい大変なんだなと思ってたんですけども、実際に自分がフィールドワークをして分かったのは、フィールドワーク最高! 自分、実験室も好きですけど、フィールドワークもすごく楽しいじゃないかって(笑)。過酷っていうのは、体力的なこととか、悲惨な生活とか、あるのかもしれないですけども、研究者として力試しができるし、やりたいことに100パーセント没頭できるフィールドワークは、最高の贅沢だと思いました。」
このように順風満帆なフィールドライフを開始したと思いきや、いきなり、大きな壁が立ちはだかった。
前野さんが砂漠でバッタを見ることができたのは、最初の2カ月だけで、その後、モーリタニアは建国(1961年)以来という大干ばつになり、砂漠からバッタが姿を消してしまった。「300キロ離れたところで、5メートル歩くと3匹バッタがいたぞっていう情報を入手して行ったら、5キロ歩いて1匹いたくらいでした。」というほど、バッタが消えてしまったのである。研究者としては大変つらいことになってしまった。
結局、2011年5月に行ったフィールド調査以来、次に前野さんが大量の調査対象と出会うのは、2012年の秋を待たねばならなかった。ぼくは2012年の早い時期に、前野さんに連絡し、機会があればぜひ訪問させていただきたい旨、伝えてやりとりをしていたのだが、「今年はバッタが出そうにありません。」と力ないメールが届きその年は断念した。