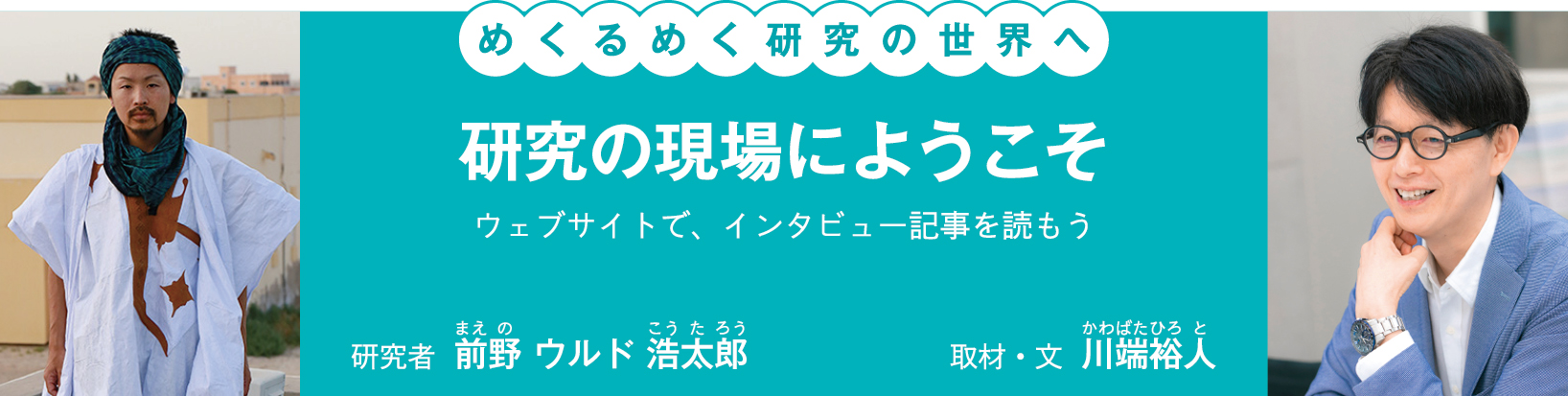第6回 | バッタ博士の研究に「アフリカじゅうが期待をしている。」
前野さんが所属しているモーリタニアの国立サバクトビバッタ研究所(=防除センターでもある)は、飛翔能力がある成虫になる前に幼虫を防除することで、大発生を抑え込もうとしている。これは、国連食糧農業機関FAOが推奨する方法でもある。
前野さんの研究拠点でもある本部から、常に防除チームが砂漠に遠征しており、ぼくが訪ねた11月時点で、長い人では4カ月、つまり7月からずっと砂漠暮らしを続けていると聞いた。
ぼくがフィールドを訪ねた2日目。薄曇りながら、朝から太陽の熱を感じる程度には天気が戻ってきた。前々日は雨でサバクトビバッタの幼虫がシェルターから動かず、前日は風が強くて薬剤散布がままならなかった(おかげで、我々はたくさん観察できた)。3日ぶりに、やっと、防除活動ができる日がやってきたのだった。
前の日に会った時には、リラックスムードだった防除チームだが、この日は朝から、キリッと準備に余念がなかった。

ピックアップトラックの荷台には、薬剤のタンクと空中噴霧器が取り付けられている。ここで使われているのは、超低量(Ultra-Low Volume) 散布 という技術だ。サバクトビバッタが移動しているところに濃い殺虫剤を少量まく。そこを通ったバッタは、殺虫剤の付いた餌を食べたり、直接体に殺虫剤がついたりして死亡する。
薬剤は人体にも有害なので、作業をする者たちは、自分たちの身体を守らなければならない。青いつなぎの防護服を着て、マスク、フェイスガード、さらに頭にはターバン状の巻物までして、防護する。そして、ランドクルーザーをじぐざぐに走らせつつ、要所要所でミスト化した薬剤をまいていくのだ。
前野さんは防除作業とはつかず離れずの距離で、まだ薬剤の影響を受けていない群れの観察を続けた。ぼくとしては、防除作業の様子もつぶさに見つつ、幼虫のマーチング・バンドも見ているという状況だ。

防除チームは実によく働く。朝の7時に準備開始し、そこから14時くらいの昼食まで、お茶を挟みつつ、薬剤をまいて回る。お茶の時間は、木陰で談笑しつつのリラックスタイムなのだが、それ以外は、もう真剣な表情の戦う男たちである。

前野さんは研究者として砂漠にやってきて、防除チームから多くのことを学んだ。そもそも、彼らが砂漠でバッタを見つけてくる。こういう時にはこういう場所にいるとか、こういう動き方をする、といった基本的なことは、日々の体験として知っている訳だし、彼らの導きがあって、はじめてフィールドに向かうことができる。
一方、前野さんは、いずれ研究成果が防除のために役立つと期待されている。研究所のババ所長によれば「アフリカじゅうが期待している。」のである。
では、実際、前野さんの研究は、現場にどのようなフィードバックをもたらしているのだろうか、あるいは将来、もたらすと期待できるのだろうか。

「基本的には、最初は教えられることばかり多くて。でも、彼らが、経験上知ってることに、自分が付け加えることもあるんです。例えば彼らは孤独相はずっと孤独相だっていうふうに信じてるんです。それで、自分が実験室で研究した結果では、その孤独相でも混み合うと大きな卵を産んで群生相が出てくるんだぞって言うと、いや、そんなわけはない、と最初はなるわけです。でも、実験結果とか示すと、『ああ、マジか、そんなの知らないぞ、野外でもありえるな。浩太郎、もっと教えてくれ。』みたいなかんじになっていくんです。」
孤独相のメス成虫が、混み合いを経験すると、群生相になる卵を産むことを明らかにしたのは、前野さんの実験室での大きな成果だ。これを知っているか知っていないかでは、警戒すべき範囲が違ってくる。
そして、さらに将来に向けて、より防除に有効な研究はできるだろうか。前野さん自身、サバクトビバッタの相変異の秘密を解き明かしたくて、実験室で、また、フィールドで研究を続けているわけだが、現地を知れば知るほど、「防除に役立つ研究を。」という思いは高まっている。
「夜、木や草に潜むのは、もう分かっているんですね。そこに薬剤をまいたらどうなるかですとか、ババ所長に1回実験をやってみたいと言っているんです。今は、昼間、動いてるやつにまいているわけですけど、夜は動かないし逃げないし。防除をやっている人たちは、木が邪魔をして薬剤が入り込まないと言っているんですけど、丹念にやればずっと効率的かもしれない、と。」
その上で、前野さんがフィールドで、これから目指すこと。
実は、前野さんは、来る4月から京都大学の白眉センターの助教の立場で、5年間、学生に指導する義務なしにひたすら研究することが許される(注:2014年現在。その後、2016年に国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに異動。)。バッタが出る時期はモーリタニアにいて、シーズンオフには京都でデータをまとめ論文を書き……という学究に専念できる時期がとれそうだ。これまで論文にまとめていなかった成果を次々と発表してほしいし、また、フィールドではさらなる研究を進めて欲しい。
ところが、意外なことに前野さんから、最初に出てきた言葉はこんなふうだった。
「3年間このモーリタニアにいて、自分の力不足をものすごく感じました。研究する能力であったり、必要最低限の経済力とか、いろいろ。その中で、特に現地の人たちが持っている知識や経験が宝箱と気づいたんですが、それを開けるための鍵を自分が持っていない。例えば言葉です。自分のフランス語では、話を引き出せない。言語という鍵を持っていない。文化や歴史、宗教も含めて、教養的な部分を、一から鍛えたい。それで、現地の人と心通じ合うことで信頼を勝ち得て、新しいサバクトビバッタの問題点を見いだしていく必要があると思っています。今度、京都大学でいろんな分野の人たちと、一緒にいろいろ仕事なり、話ができる環境に行けるのは、願ったりかなったりです。」
昆虫学の研究者が、アフリカのフィールドに飛びだして見つけた課題が「教養」だったというのは、肝に銘じるべき至言かもしれない。
その一方で、長期的には、前野さんの「野望」は収集がつかないほど広く深い。
「1945年にイギリスにバッタ研究所っていうのができまして、20年近くにわたって行われた研究が、今でもバッタ学の基礎となってるんです。そのときに例えば幼虫の体色だったらこの人、形態だったらこの人、行動だったらこの人みたいな、レジェンド的な先駆者たちがいました。その研究の伝統がいったん途切れてしまっている部分があるので、それを自分は全部カバーして、あらためてサバクトビバッタ研究の基礎を立て直したいんです!」
さりげなくも、欲張りな野望だ。さらに言う。
「今まで、研究者の成果っていうものは、論文の形になって初めて人前に出てきたわけですが、自分は、研究者の研究している姿、どういう思いで研究しているのかとか、そういうドラマチックなプロセスもみんなに知ってもらいたいんです。そして、より身近にサイエンスを感じてもらいたい。京都大学の白眉センターの5年間はまだ基礎固めで、レジェンドたちの研究を全てカバーしきれないと思うんですが、いつかそれもきちんとやっていきたいんです。」
野望は果てしない。5年後、10年後の前野さんは、何をしているのだろうかと、本当に楽しみだ。ぼくとしては、砂漠のフィールドで昆虫を見て、疑問を次々と解決していく昆虫探偵、ファーブルのような研究者になっていただけたら、と期待すること大なのである。